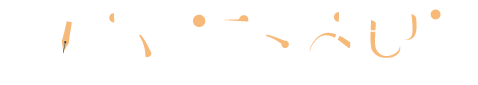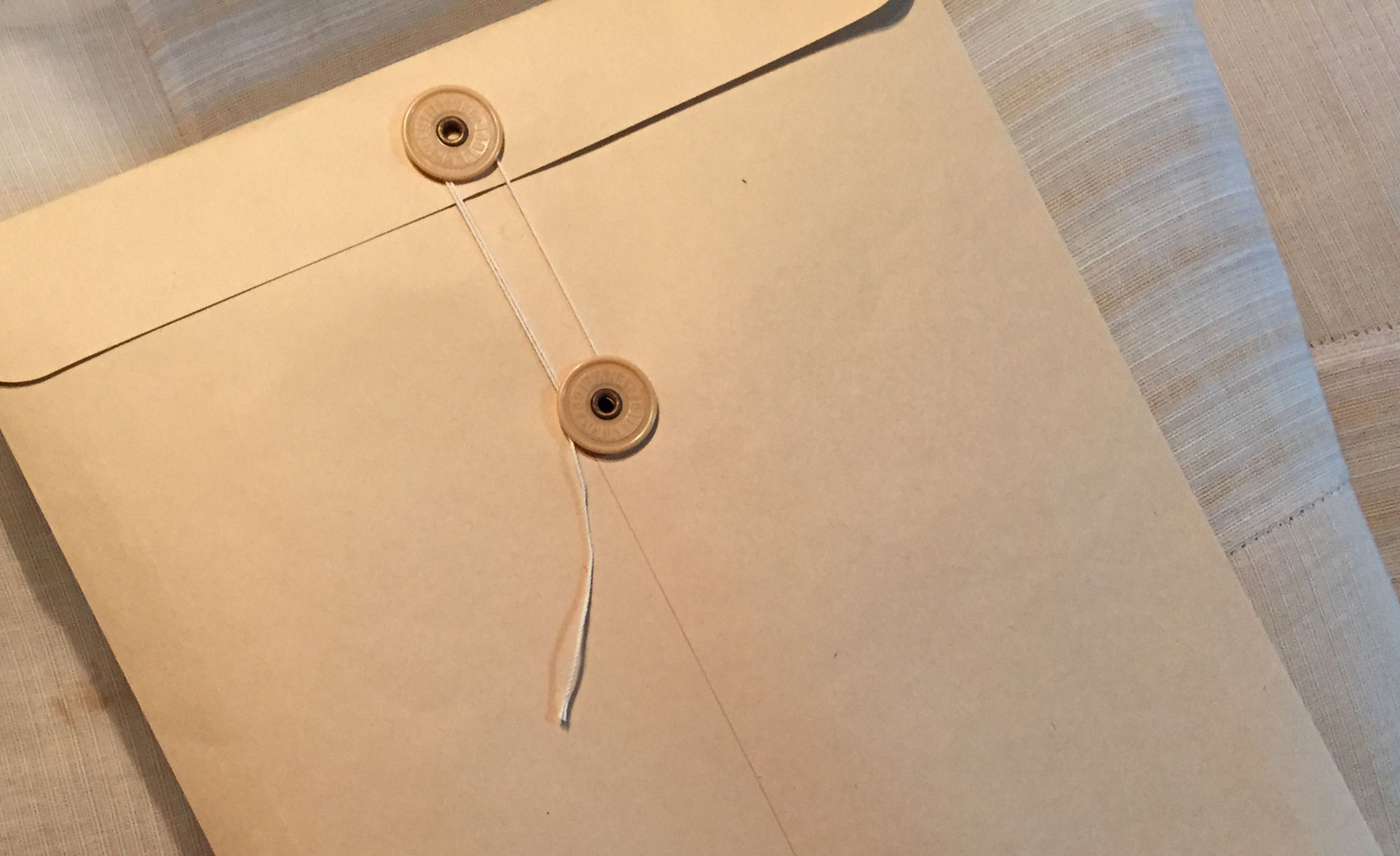哲学 第2課題
「 プラトンの「洞窟の比喩」を簡潔に説明したうえで、教科書の筆者が哲学という営みをどのようなも のとして捉えようとしているかをまとめなさい。 」
レポートの参考にどうぞ。
全体的・部分的問わず、剽盗・転載はご遠慮ください。
レポート本文
(1)
「洞窟の比喩」とはプラトンの「私たち自身を取り巻く状況」についての例え話で、概要は以下の通りである。
生まれてからずっと暗い洞窟の底で暮らす囚人がいる。彼らは鎖で洞窟の壁に視点を固定され、他の場所に出たことがないため、この見える範囲こそが世界の全てだと思っている。彼らから死角になっている後方に火が灯されている。その火と彼らの間には人形劇のような舞台があり、舞台のものは火に照らされ、囚人たちの前の壁に影を作る。彼らは自分たちの後方に空間があることを知らないので、映し出される影こそが実体だと考える。彼らはその影について研究し、詳しい者は知者や科学者と呼ばれた。
ある時、一人の囚人が鎖から解放され、自由に歩き始めた。初めのうちは歩くことも見ることもぎこちなく、慣れるまで時間がかかったが、やがて周りのものを自由に見ることができるようになり、影の正体を知った。また洞窟以外の世界があることを知り、外の太陽の存在に気付き、自分が今まで洞窟の囚人だったのだと悟った。彼は仲間にこのことを伝えたいと思い、再び洞窟の中へ戻ったが、仲間にとって彼の言葉は理解不能で不愉快なものだったため、死によって黙らされた。
(2)
筆者の考える哲学とは知的な冒険のことであり、その芯は「自問自答すること」と「本を読むこと」に絞ることができると考える。以下にそれぞれの特性と理由を記す。
前者の「自問自答すること」だが、これは今まであらゆる哲学者たちが行ってきた方法である。自らの心に、精神とは何か、道徳とは何か、神とは何か、現実とは何かといった謎を問いかけることである。それは常に批判的な視点から行われるもので、今まで持っていた常識や観念にとらわれることなく、むしろそれらを厳しい目で見つめ直さねばならない。これは、哲学という分野には参考にすべき原理や不変の学説が存在しないためであり、あらゆる考え方は完璧ではないためである。逆にいえば、自分の答えは自分の中にしかないということでもある。これを行うのに必要とされるのは真理への探究心である。哲学を行う権利は誰でも持っている。それを行うことで、たくさんの学びを得ることができ、有意義で良い人生を送るために不可欠な精神的訓練を受けることができるのだと筆者は語っている。謎を見つけることが哲学することの第一歩であり、思考し悩むことが哲学の本分である。
他方「本を読むこと」とは歴史上の無数の哲学者とともに冒険することである。彼らが一体どんなことを考え、悩み追求してきたのかを彼らの本を読むことで学び、自らもその問題を考えてみることである。これは筆者が哲学者のあらゆる疑問や問題の多くは、ギリシアの哲学者たちが語り記したことの再検討や練り直しであると考えているためである。そのため、本書でも哲学と言う言葉の本来の意味に立ち返ることがなされた。この「本を読むこと」は大事なことであるが、一方であくまで前者「自問自答すること」の補助的なものである。この行いは自らが思い悩むのに必要なヒントを与え、考え方の手本を示してくれる。本を読みあらゆる哲学者の考え方に触れ、その上でそれを肯定してもいいし、否定し新しい答えを生みだしても良い。大事なのは一緒に考えることであり、彼らの本を読み進めると同時に、共にその問題について悩んでみること、積極的に自らも問題に取り組むことが、「彼らと共に冒険をする」ことなのである。本を読むということは考えるきっかけを掴むということであり、真理に近づくための行いである。
哲学をするということは、自らの心に問いかけ、悩み、自らの根底に立ち返ることである。それに適した行いは、シンプルに自らの心に「問いかける」ことと、数多の哲学者たちの本を読み、どんなことが問題とされ、どのように解決を導きだされてきたのかを「知る」ことである。筆者にとって哲学とは何よりも自らの心に問いかけることである。その問題提起は自ら行ってもいいし、哲学者たちの本を読むことで得ても良い。大事なのは思考すべき問題が発生した時に自らの心に問いかけることであり、自分なりに答えを模索することである。この一連の行いを筆者は「知的な冒険」であり、「哲学」だと考えている。
参考文献
- 「哲学の冒険」ルイス・E・ナヴィア 武蔵野美術大学出版局 2002
- 「国家」プラトン 岩波書店 1979
オススメの参考図書
↑↑理解はできるけど、自分の言葉でまとめあげるのは難しい!プラトンの国家は読んでおきましょう。ふーーーー大変な科目でした。